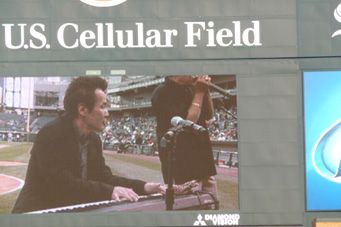2010年6月1日(火曜日) あははは、もう6月・・・。いやね、ちゃんと4月も日記をつけてましたよ、下書きで。でも、気が付けば5月はメモすらない完璧な空白。先週ぐらいから気温は30℃を超える日が続いているし、今日はついに今年初めてエアコンも点けたし、とりあえずリセットということでよろしくお願いします。 Vince Agwada のレコーディング・リハを彼の自宅で。ヴィンスの3歳半になる息子は、大好きな父親と遊びたくて仕方がない。父親を取られた腹いせに、使用済みの紙オムツを投げつけられた。 2010年6月3日(木曜日) カナダのモントリオールから遊びに来たロシア人チェロ奏者に慕われている。 弓を使う擦弦楽器(さつげんがっき)でも、ヴァイオリンはブルース業界のごく一部に見られるが、チェロは記憶にない。CDなどで特定の曲に採用されるバック・グラウンドを除き、これらの楽器の音色は「オレたちの演るブルース」に合わないと思うし、良い評価を聞いた覚えもない。奏法にも因るのだろうが、リズムの出方が弱くクラシック風が漂い過ぎたり、逆にカントリーっぽくなってしまったり、極論をいえばブルースに寄ってこない。何れにしても、演奏者が少ないという現実が、弓弾きはウチらと肌が合わないことを物語っている。 また、立って弾けるヴァイオリンと違い、チェロは椅子に座るので場所を取る。ドラムもキーボードも設置ものだが、最初から乞われて存在しているため、大きな顔で空間を占有できる。しかし、かのチェロは本来要求される楽器ではなく、セッションに飛び入り参加しているに過ぎない。そのため、持参のアンプと折り畳み椅子を、人が演奏している脇からゴソゴソとセッティングしている様(さま)は、傍(はた)から見ていて隣り合わせの者には迷惑そうであった。 木曜ロザのジャムには、いろんなミュージシャンがやって来る。 早く演奏したい、仕切りたい、歌いまくりたい、ソロを取りまくりたい、間の手(唄の合間に音を埋める)を入れまくりたい、ずっと演っていたいなど、各人の希望は様々で、それらの前向きな我(が)が遠慮なしに表出されると、「朝まで生討論」のなじり合い、または反対意見を押さえつけ、一方的に話しだす司会者のような失態を晒すことが少なくない。そしてチェロ氏は、間の手を入れまくりたい、ずっと演っていたい方だった。 表向きのバンド・リーダーはジェームス・ウイラーだが、真の仕切り(誰がいつ、どれくらい演奏するかなどを決め、MCまでする)はドラマー兼雇い主のトニーである。そのトニーは目先の変わったゲスト、例えば女性、子供、相当なお年寄り、珍しい楽器奏者などに鷹揚だった。だからチェロ氏は、一旦ステージへ上がると最終セットまで居続ける。 オレは迎える側だから一応泰然としてはいるが、他の演奏者や客達が「何でアイツだけずっと演っているんだ、おまけにブルース知らないし」と不平を申し立ててくる。「まぁ短期滞在者だし、トニーが何も言わないから」と宥(なだ)めるものの、チェロ氏には「アンタもう下りてくれる」と言わせ難い雰囲気があった。彼が初めて来たときにそうしてしまったから、トニーも今更「2.3曲で下りてくれますか」とは言えないのかも知れない。 ブルースのフレーズは別にして、クラシックの腕は確かなので、「こうしたら、ああしたら」と当たり障りのない意見を述べる。彼は謙虚に応えようとするが、オレのアイデアにも限界がある。するとまた間の手を入れまくり、他の奏者の音と戦い始めるのだった。 そういった苦労を、元オレのピアノの生徒で、たまたま遊びに来ていた国立音大声学科出身のK子に話すと、頷きながらもどこか納得していない様子だった。はっ、お前は以前、ピアニカを吹きまくっていたな・・・。 2010年6月5日(土曜日) 持病である膝の治療のため故郷のミラノに半年以上滞在していた、ローザスのママ・ローザ(ロザ・ママ)の「お帰りパーティ」をSOBで。 久し振りに会った知り合いのカップル。女性がオレの顔へ親しげに頬を触れさせた。そのキスするでもない微妙な距離(!)には慣れているが、たまに唇へ最接近させる思わせ振りな方もいらっしゃる。 そのとき、隣のオヤジと握手をしながら、何故か右頬に痛みを覚えた。それは5センチ四方に渡って大量にチクチクと発生している。 オッサンッ!何でオレに無精髭の頬寄せとんネン! 2010年6月7日(月曜日) アーティスでアーティスの誕生会。プレゼントを買ってなかったので、彼女へ僅かばかりの現金を渡すつもりだとビリーに告げると、大将は財布から紙幣を抜き取り言った。「足しておけ」・・・よっ、オトコマエ! 今日も来ていたロシア系カナダ人のチェロ奏者のV(2010年6月3日付け日記参照)は、ビリーから名前を覚えてもらえず、"Mellow Fellow"(しぶいヤツ)とチェロを掛けて"Mellow Cellow"と呼ばれていた。そしてMCのモーズはメロウ・チェロウをなかなか呼ばず、ステージへ上がったら上がったで、他のミュージシャンから自分らの立つ場所がないと邪魔者扱いされていた。バー・カウンターが間近で床と同じ高さの舞台のアーティスでは、ほとんどの客から椅子に座ったVが見えない。それでもめげない彼が気の毒になり、オレの真ん前に避難させる。さすがのVも事情を察したらしく、しばらくすると自らチェロを片付け始めた。 こういう試練を乗り越えて、オレらが一緒に演りたいと思えるようなミュージシャンになってほしい。もしVが痛みを感じていたら、それがブルースを紡ぐ源になるのだから。 2010年6月8日(火曜日) ヒイヒイいってる。今週はありがたいことに10本だが、20曲を採譜して覚えなくてはならない。盟友のチャールズ君のライブなんか、ほとんどポップスだし・・・とかいって、スタジオ仕事を1本延期させてもらって、リハを1本トバしてしまいました。それでもまだヒイヒイいってる。 2010年6月9日(水曜日) 移転新装のバディ・ガイズ・レジェンズのイベントにSOBと。 思わぬ早い帰宅(午後9時過ぎ)に、NHL(北米アイスホッケー・リーグ)のシカゴ・ブラックホークスが優勝する瞬間をテレビで観ることができた。別に普段からブラックホークスを応援しているわけじゃないが、49年振りとなるとやっぱりね。 昼と変わらぬ交通量の街にタバコを求めて車を走らせていると、「通りに溢れる」とまではいかないが、いたる所で人々が優勝を祝っている。それに呼応したクラクションの嵐に、オレも自然と「ピッピー、ピッピー、ピッピィイイ」。ここに至って無音の運転者はシカゴの住人にあらず。人気のない交差点でも誰かが「プップップゥウ」と始めると、面白いように警笛の波は広がってゆく。 日常(人に注意を促す)とは違ったクラクション多用は楽しい・・・ん、楽しい!?そういやオレは、大昔にもこうして楽しんだ想い出があるような気が・・・。ただ、何かを祝ってとかではなく騒ぐだけが目的の、そして周りはもっといろんな音色が渦巻いていて、オレのセドリック230GXだけ「大型バス」のような「ふわぁあーーーん」の大音量だったけれど。 2010年6月11日(金曜日) ああ、まるで忙しい夜勤のような一日がようやく終わった。 昨日は、シカゴ市に隣接するエヴァンストンにできた新しいクラブ"SPACE"でイベントがあり、ドラムのサム・レイやボブ・ストロジャー、ウイリー親子らとご一緒した。メディア(雑誌、ラジオ、記録映像など)のインタビュー(あの方達のね)の関係でサウンド・チェックが先となり、オレには早朝の午後5時前に起床していたため、元々が寝不足だった。それなのに何故か寝付けず、今日は午前11時に起きたから4時間程しか睡眠が取れていない。 楽しいシカゴ・ブルース・フェスティバルも、今年の出番は今日の2本のみ。 昼の1時過ぎから、ブルフェスの小さなステージでロブ・ストーンたちと75分。出演者用に駐車場は用意されているし、機材は現場に揃っているから搬出入がなくてラクチン。でも気温が30度を超えていて暑い。メイン・ステージの快適な楽屋と違って、その他の会場の控え室は野外テント・・・んなとこ居れるか! 汗だくの衣装のまま一旦おウチへ帰って(片道25キロ)シャワーを浴び、サンドイッチを少し啄(ついば)み、着替えを持って再びブルフェス会場へ。6時過ぎからロブ・ブレインの爆音ショウのお手伝い。彼のデビューCDにはオレも一曲参加しているから、即売で40数枚売れたのは嬉しかった。 その後、普段は互いの仕事が重なってなかなか会えないミュージシャンらとグタグタしたり、ローザスの物販テントに寄ったり、辺りをちょこっとブラブラしてから、移転・新装したバディ・ガイのクラブ、レジェンズへ。海水浴帰りのような身体の火照りを感じながら、「えっ、これからまだSOBとお仕事ぉ?嫌だぁ、もうおウチへ帰りたぁい」と、日本で働く大半の方々からは失笑されそうな愚痴が出る。 二階に在る綺麗で真新しい楽屋のまっさらなソファでウツラウツラしていると、「はぁい」という挨拶が聞こえた。適当に返事し、しばらくして薄目を開けると、ドアの脇にチェロケースと小さなアンプが置かれている。はっ、もしやメロウ・チェロウ?(2010年6月3日、7日参照)。間もなくやって来たギターのダンが、それらのセットを見て絶句する。彼はオレに「なんで、何で、どーしてなの?」と責めるが、んなことは大将に言え。きっとオヤジは何も考えず、「いいよ、おいで」と言ったに違いない。 と、今度は店の従業員がいきなりドアを開け、「今ここに、チェロを持ったヤツが来なかったか?ちっちゃいアンプ提げて」と問うてきた。SOBと一緒に演奏することになっている者だと入ってきたが、ゲストリストに名前はなく、気になったんで確かめにきたらしい。渋面の二人は、「ああ、知ってるヤツだから大丈夫」と応えるしかなかった。 メロウ・チェロウに挨拶されたビリーは、一瞬面食らったものの、やはり最後のセットの終わりの方でステージへ上げた。もう大将の浅慮には慣れている。各自の役割が決まっていて、誰も入る隙のない曲にまで彼は居座ることとなった。 そして懸命に手で「全タマ(倍・全音符=一・二小節、ずっと同じ音を弾き続ける)」を指示するオレを無視して、ピアノやギター、大将のハーモニカと音をぶつからせながら、メロウ・チェロウはヨーヨー・マ(世界的なチェロ奏者)と化していった。 帰宅、午前3時過ぎ。 2010年6月13日(日曜日) 盟友、チャールズ・マックくんのライブのお助け。管楽器二つと、コーラス二人が入った大所帯で楽しみ。 昨日はロブ・ストーン、クリス&パットらとハウス・オブ・ブルースで普通にライブ。明日アーティスでSOBのレギュラーはあるにしても、金曜日の一日を考えると「通常営業」に等しい。ましてや今日は現場機材で持込みなしの一時間のみ。但し、チャールズくんのポップスなオリジナルに誰某のカバーなど、宿題が多かったので苦労したが。 ガン撲滅のためのイベントで、会場は劇場を小さくしたようなロック系のクラブ。他の出演バンドもロック色の強い爆音ものが多かったが、こういうところで別業種のミュージシャンが頑張っているのを見ると、ちょっと感慨を覚える。 そしてチャールズくんは、一曲ごとに自作の譜面をあたふためくっているオレをよそに、採譜に一番時間を食ったジェイミー・カラムの曲をトバしてくれた。おいっ、オレの時間を返せ! 2010年6月14日(月曜日) ブルフェス明けの週だから、最後のシカゴを楽しむ州外や海外からの客で賑やかなアーティスだった。 休憩中、人混みをかき分けてGとRが近付いてきた。「おう、アリヨ、こいつ知ってるだろ?」と、小柄だががっしりとした黒人を押し出す。えっ!?会った記憶はないのに、初対面ではない様な気も。「アイヴァン・ネヴィルだよ」と紹介されて、「ああ、ああ、どうも初めまして」と応えたもののまだピンとこないオレは、「その偏狭な音楽知識で、よくこの業界を生きてるな」と言われても仕方がない。 アイヴァンに「ここ喧しいから、外いこう」と促され、表でしばらく話していてようやく気が付いた。あはっ、アーロン・ネヴィルの息子・・・。大昔にオレはアーロンのヒット曲"Tell It Like It Is"を、永井隆さんとデュオで演っていたことがある。そういや親父に似てるわ。妙な既視感はそれか。 それにしてもニューオリンズの山岸さん。どこまで有名人(この業界での)と知り合いやねん、と言いたい。アイヴァンは最初の挨拶で「ジュンは知ってるか?」と訊いていた。「それじゃぁ、ジュンと一緒に演ってる誰某(だれそれ)や某(なにがし)も知ってるな。俺も一緒に仕事してるんだ」。誰某に某の名前を聞いたことはなかったが、きっと有名な人(もしくは有名なグループの人)なんでしょ。「へぇ、そりゃすごい」と適当に相づちを打つ。 一時期SOBでキーボードを弾いていたというアイヴァンが、独特の甘いファルセットの親父とは違った、勢いあるだみ声で唄いだすと、ブルース観光客が一斉に前へ押し寄せカメラを向けた。ギターをGへ渡して手持ち無沙汰のダンに、「あいつ、アーロン・ネヴィルの息子って知ってた?」と問うと、「えっ?!ホントォ?そういや、顔が似てるね」と驚く。ははぁん、お前も・・・の口やな。 2010年6月18日(金曜日) シカゴ市の北の郊外に在るエヴァンストンの新しいナイト・クラブ、SpaceにSOBが初登場。 その平屋の建物は、レストラン、ミュージック・ホール(250人収容)、録音スタジオが、ウナギの寝床様に一本の通路で繋がっている。スタジオ脇の広いコンコースには、ゆったりとしたソファにテーブル、椅子などが配置されていて、出演者はレストランから自由に食事を取ることができ(契約によって違うのかも知れないが)、演奏時間は8時から一時間のセットが二本のみ。大抵3セット/時間か、2セットでも一本が長時間だし、終演が午前2時近くになることを考えると条件(お支払いも含めて)は格段に良い。 ベースのニックが、「わぁ、なんて素晴らしい仕事。次の出演予定はいつ?来月?来週?明日でもイイよ」と戯けるが、オレの自宅から車で12分の距離なんで毎日でもよろしい。 共同経営者のデイブ・スペクター(ん、同じ名前でシカゴ出身のタレントが日本にいなかったかい?)は、老舗のデルマーク・レコードから10枚以上のソロ・アルバムを出している、地元では有名なミュージシャン。身長が190センチを超える大男で、従業員への態度も自然と威厳に満ちている。 ところがSOBの控える場所へくると、途端に相好を崩す。媚びへつらうとまではいかないが、先輩に気を遣っている様が柄を小さく見せる。若いダンを除くと、オレたちはデイブがまだギターのコードしか弾けない学生時代から知っていた。当時ハルステッド通りの老舗クラブ"B.L.U.E.S."のドアマンだった彼は、それぞれが別のバンド(ビリーやモーズはSOB、ニックはサン・シールズ、オレはジミー・ロジャースやヴァレリー・ウェリントンなど)で演奏しているオレたちを、憧れの目で見上げていたのだろう。 一人前といっては失礼だが、デイブもミュージシャンとしてのキャリアを積み、今や大きなナイト・クラブの責任者のひとりである。雇う側として、こちらとは対等以上の立場であるにもかかわらず、何かの序列を認めている彼には好感が持てた。たとえローカルではあっても、オレたちが一線で演り続けているからこそだろう。 暗い通路でデイブがすれ違い様に、オレの脇腹を指で突ついた。ニッと笑ういたずらっ子の目は、互いがまだ二十代だった頃の無邪気さのままに、茶目っ気が発揮できる喜びを謳っていた。そしてこちらも、なぜか嬉しくなる。 しかし、お前加減せえよ。アバラが痛い・・・。 2010年6月23日(水曜日) 買い物に出掛けようとしていた夕方、突然の雷鳴と豪雨にテレビを点けると、シカゴ市を含むクック郡全域に、雷雨・洪水(浸水)警報と竜巻警報が発令されていた。地元局はどこも番組を変更し、天気図を示しながら、キャスターが緊張した面持ちで最新情報を伝えている。イリノイ州南部での竜巻被害(米国中・中西部はメッカ)はたまに聞くが、市内での発生は聞いたことがない。 「(ウゥウ〜〜ーー)この警報が聞こえたら窓からは離れて、地下室やシェルターがあればそこへ、なければ一階の建物の中心(隅から壊されていく)へ避難してください。バスルームに居て助かったという報告もあります。また外出している人は・・・」 日本の台風の季節を思い出させる非常時の如き報道だが、ここらで被害があっても突風で窓ガラスが割れる程度のことだろうと、被災の可能性はまったく考えなかった。進路予測のできる台風と違い突然発生する竜巻は、「発生確率」に基づいた注意報や警報が積乱雲の移動に伴い広範囲に及ぶ。しかし竜巻自体は局地的なため、警報の解除は早そうに思えた。それでも小一時間は出られそうにない。 大きな窓から荒れ狂う嵐の屋外を眺めていると、テレビで鳴っていたのと同じ音が聞こえてきた。さすが「オズの魔法使い」の国。市内にも警報機が設置されていたことに驚く。 空襲警報って、きっとこんな感じだったのかも知れない。自分の近くに爆弾が落ちるまでは、現実と乖離した危機感なんて誰も持ちたくないもの。警報の先にある悪い結果を打ち消しながら、変わらぬ明日を信じている。理屈よりも、恐怖の実感を持つ人にしか警報は意味がないのだ。だからオレは、戦時下の人々や過去の被災に遭った地域を想いながら、自然のショウを鑑賞していた。 幸いニュースとなるような被害はなかったらしい。おそよ一時間半程すると、晴れ上がった西空に傾いた陽が、盛んに夏を慈しんでいた。 2010年6月29日(火曜日) シカゴで10数年頑張っていたTが日本へ帰って行った。ピアノだけではなく、近年はオルガン奏者としても自己名義のユニットなどで忙しくしていたが、次のステップを考えて帰国を決めたのだろう。 ジャズ界を職場としたTとオレの現場が重なることは少なかった。それでもこの歳の離れた後輩からは、ジャズの知識などを含めて大いなる刺激を受けたし、彼の活動に触発されることも多かった。 互いを理解し、本音で音楽の話ができる仲間が、またひとり去っていく。シカゴに未練なく、晴々とした表情でオヘア空港の搭乗ゲートへ向かうTを見送りながら、彼を少し恨めしく思った。自分の演りたい場所はシカゴが一番にしても、オレはいつまでこのレベルにしがみついているのだろう。 Tから与えられた最後の揺さぶりも、別便で今日帰国したS君からの別れの挨拶メールに淡く消えゆく。京都からブルース観光で来ていた彼も、そこまでオレが考えるとは知る由もない。 追伸:先日Buddy Guy's Legend にカルロスジョンソンを見に行くとなんと、本人がいました。それだけでも鼻血が出そうでしたが、なんとストーンズのロンウッドが来てて2曲くらい3人で演奏し、失禁しそうになりました(笑) なるほど、彼はバディ・ガイを見ただけではなく、ロン・ウッドとも遭遇した喜びを伝えているに過ぎない。普段のオレなら、「どうせならロン・ウッドも、カルロスよりウチらのライブ中に姿を見せろよな」と吐くだろうが、この追伸から一気にカルロスのサイドマンたちを思い遣った。 こういった機会に、他人は「気に入られて誘われるかも知れませんよ」と軽く言う。しかしサイドマンとして知り合う限り、将来を明るく照らす美味しい話になる可能性が極々少ないことを、オレは経験上よく知っていた。数年前、クラプトンやサンタナ、ジェフ・ベックらのバックを務めたのに、上部関係者のみの接触で囲い込まれ、彼らと挨拶さえ果たせず悔しがっていた、バディ・ガイのキーボードのマーティまで思い出す。 先ず、それら超有名人の方々と気軽に会話できる立場というものがある。オレたちがリーダーを差し置いて前へ出るわけにはいかないし、もとより、そのリーダーが知っている人でなければ紹介さえされない。先方から声を掛けてくれる気さくな人もいるが、どちらにしても、その場でお友達にはなれない。 ロン・ウッドは、バディ・ガイと会うために来店していたはずだ。仮にカルロスが知られていたとしても、二人がメル友とは思えない・・・カルロスは意外な有名人と知り合いだったりするから、断言はできないけれど。いずれにしても、ゲストとして「今度遊びに来てね」と誘われるのはリーダーで、バックは歯牙にも掛けない人が多いのだ。 一方でそれは恋愛の横恋慕に似ていて、万が一こちらの音が超有名人の琴線に触れたとしても、彼らがリーダーの頭越しに連絡先を訊いてくることは少ない。あの方々もそれぞれのメンバーをお持ちで、よっぽどの一目惚れでさえ微妙なタイミングがあるし、儚い相思相愛が本格的な恋愛に発展するかどうかは、自然に再会できる条件に拠る。スタジアムやアリーナとローカル・クラブ、大手の録音スタジオと独立系とでは、職場環境があまりにも違うのだ。 何も、やりたいことを抑えてまで、かの人たちに仕えたいと願っているのではない。リーダーとなって、たまのゲストに呼ばれたいのでもない。演奏の質や条件など、以前より向上しているのかと自らに問うているのだ。 過去何件か、実現したかも知れない超大物からの誘い。積極的に応えなかったのは、己の覇気の欠けていたことが原因だった。直ぐにできることは、近くに居る人との共同作業だということは分っている。乞われてもいるし構想もあるのに、何故か気が重い。オレには大きな障害があるからだ。それは現状に甘えて自己研鑽せず、何年も怠って錆び付いた「努力」というありきたりな重しで、「覇気」と共に人生で一番苦手なヤツであった。
|